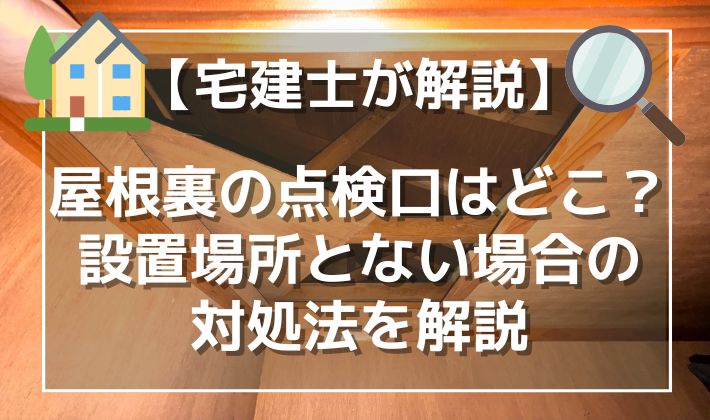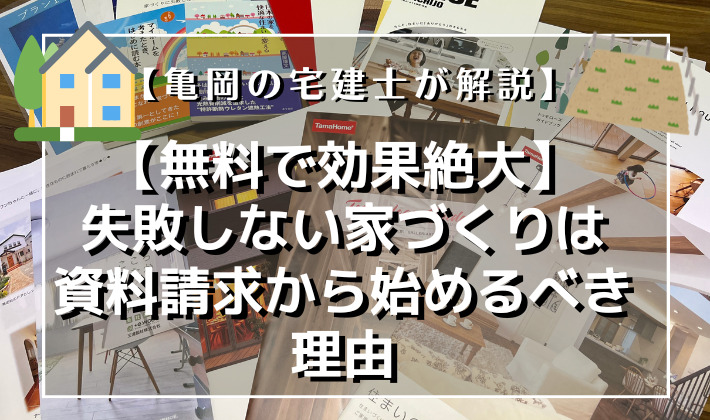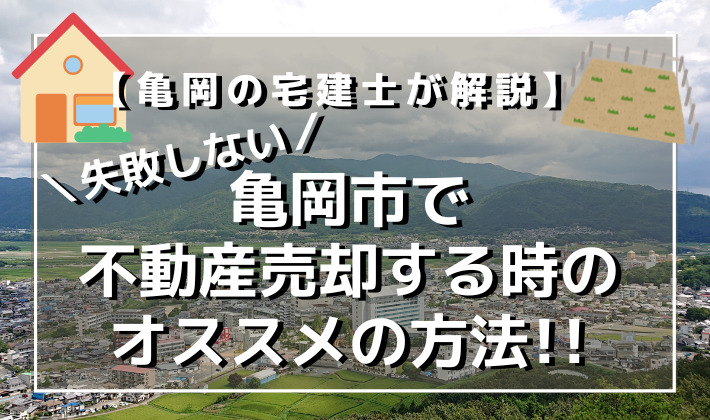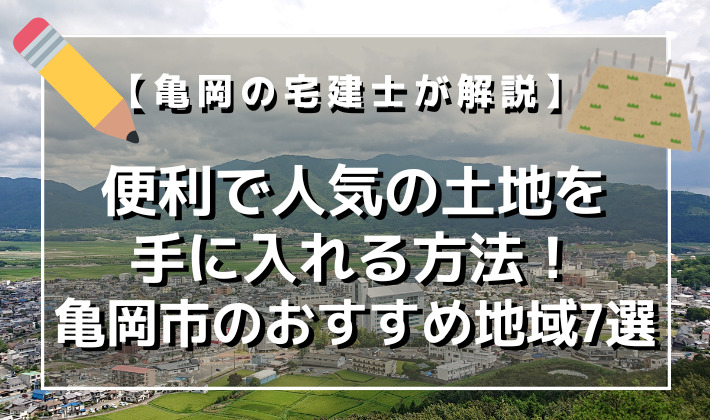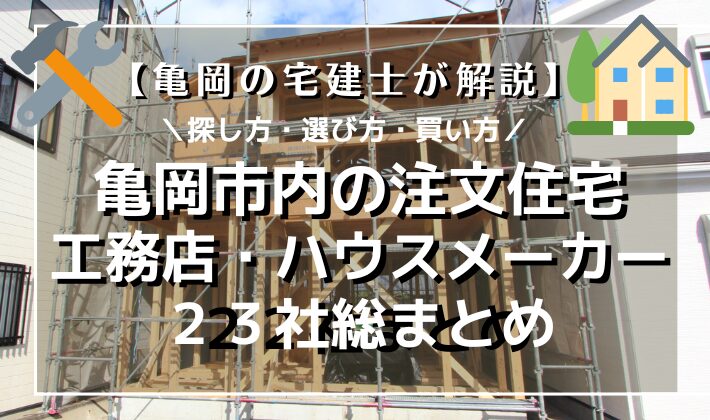屋根裏の点検口がどこにあるか分からない人
「屋根裏を確認したいのに、点検口が見当たらないどこにあるの?」
屋根裏の点検口がどこにあるのか分からず困っている人は多いのではないでしょうか?
屋根裏点検口は住宅ごとに設置場所が異なり、分かりにくい家もあります。
一般的にはクローゼットや押し入れの天井、にあることが多いですが場合によっては、居室の端や廊下、ロフトにあるケースなど設置場所はさまざまです。

しかし、すべての住宅に点検口があるわけではなく、古家には無い場合も多いの注意が必要です。
この記事では、屋根裏点検口の設置場所や探し方、点検口がない場合の対策について解説し、屋根裏に入る場合の注意点にも触れていきます。
適切なメンテナンスを行うために、ぜひ参考にしてください。
この記事のポイント
- 屋根裏点検口の一般的な設置場所や探し方
- 屋根裏点検口がない場合の対処法
- 屋根裏点検口を後付けする場合のオススメの場所
- 屋根裏点検時の注意点や必要な道具
>>屋根裏の換気扇はつけっぱなしで問題なし?効果や注意点を解説>>
屋根裏の点検口はどこにある?設置場所と探し方、ない場合の対処法

屋根裏の点検口は、多くの場合にクローゼットや押し入れの天井にあることが多いです。
以下の点で解説していきます。
- 屋根裏点検口はどこにありますか?
- 屋根裏の点検口は義務ですか?
- 屋根裏の点検口がないとどうなる?
- 点検口がない家の対処法とは
- 天井点検口を後付けする方法と費用
- 点検口を後付けするオススメの場所と注意点
屋根裏点検口はどこにありますか?
屋根裏点検口は、住宅の天井部分に設置されている小さな開口部のことです。
通常、屋根裏の点検やメンテナンスを行うために必要なものであり、主に収納スペースやクローゼットの天井、または廊下の一角に配置されていることが多くあります。
一般的な設置場所としては、以下のようなポイントが挙げられます。
クローゼットや押し入れの天井
屋根裏点検口は、クローゼットや押し入れの天井に設置されているケースが一番多い です。
和室の押し入れでは、天井板の一部が動かせる仕様になっている場合があります。分かりにくいかもしれませんが、押し入れの天井を上に押してみてください。
複数の部屋に収納がある場合は、どれか1つにしか点検口がない場合もあるので、すべての部屋の収納上を探しましょう。
下の写真の押し入れの場合、赤丸の部分が点検口になっています。

この家の場合、戸袋の上にあるので点検口に入るスペースが狭いので注意が必要です。
下の写真のように押し入れの天井の一部を上に押し上げることで、開くことが可能です。

無事に屋根裏に入ることができました。

点検作業を行う際は、荷物を一時的に移動し、脚立を使って安全に開閉できるようにしましょう。
下の写真は、押し入れではなく半帖ほどの大きさの収納です。

この収納の上にも点検口があります。

発見しにくいと思いますが、ほとんどの場合で、どこかの天井を押し上げることが可能です。
廊下や居室の天井

屋根裏点検口が、廊下や居室の天井に設置されていることもあります。
この場所に設けることで、天井裏へアクセスしやすく、作業スペースも確保しやすいというメリットがあります。
ただし、リビングや寝室などの目立つ場所に設置されていると、インテリアの美観を損ねる可能性があるため、デザイン性にも配慮する必要があります。
ロフトや屋根裏収納の中

ロフトや屋根裏収納がある住宅では、その内部に点検口が設置されていることがあります。
屋根裏に近いため最もスムーズに点検作業が行えるという利点があるためです。
ロフトの天井が低い場合や荷物が多い場合は、点検時にスペースを確保する必要があるため、事前に整理しておくとスムーズに作業が進みます。
屋根裏の点検口の設置は義務ですか?
屋根裏の点検口は、すべての住宅に設置が義務付けられているわけではありません。古い家の場合、点検口の無い家も存在ます。
ただし、特定の条件を満たす住宅では、設置が必須となる場合があります。
「長期優良住宅」 や 「フラット35」を利用して建てられた住宅では、維持管理のしやすさを考慮し、点検口の設置が義務化されています。一般的な戸建て住宅や中古住宅では、法的な義務はなく、設置の有無は建築会社や設計者の判断に委ねられています。
屋根裏の点検口がないとどうなる?

屋根裏の点検口がないと、住宅のメンテナンスやトラブル対応に支障をきたす可能性があります。
屋根裏は普段目にすることがない空間ですが、雨漏りや害虫被害、断熱材の劣化などが発生しやすい場所です。点検口がないと、これらの問題を発見するのが遅れてしまうので、後付けでも設置することをオススメします。
- 雨漏りや水漏れの発見が遅れる
天井にシミができて初めて雨漏りに気づくこともありますが、点検口があれば早期発見が可能です。放置すると木材の腐食が進み、修繕費用が高額になることがあります。 - シロアリや害虫被害のリスクが高まる
屋根裏は害虫の侵入経路になりやすく、点検口がなければシロアリやネズミなどの被害を確認できません。気づかないうちに被害が拡大し、住宅の耐久性に影響を与えることもあります。 - 断熱材の劣化をチェックできない
断熱材は経年劣化するため、定期的な点検が必要です。劣化を放置すると、冷暖房の効率が悪くなり、光熱費が増加する可能性があります。 - 修理時の工事費が高額になる
点検口がない場合、トラブルが発生した際に天井を一部解体しなければならないケースもあります。このような場合、工事費が余分にかかるだけでなく、修理期間も長くなるため、生活に支障が出る可能性があります。
リスクを避けるためにも、屋根裏の点検口はできるだけ設置しておくことが望ましいです。
点検口がない家の対処法とは
点検口がない家では、メンテナンスの際に不便を感じることがあります。
特に雨漏りが発生している場合に、原因となっている場所の特定もしずらいので、点検口がない場合は、後付けで設置することをオススメします。
適切な場所に新たに開口部を設けることで、メンテナンスの利便性を向上させることができます。費用はかかりますが、将来的な点検や修理のしやすさを考えると、設置するメリットは大きいでしょう。
天井点検口を後付けする方法と費用

天井点検口を後付けすることで、屋根裏の点検やメンテナンスが容易になります。特に築年数が経過した住宅では、雨漏りや断熱材の劣化を早期に発見するために点検口を設置することが重要です。
DIYで設置することも可能ですが、梁や配線がある場所に開口を作ると問題が発生するため、知識がない場合は専門業者に依頼することをオススメします。
後付け工事の方法としては、天井に開口を作り、既製品の点検口を設置するのが一般的です。市販の点検口は、サイズや素材が豊富に揃っており、施工後も目立ちにくいデザインのものを選ぶことができます。
設置にかかる費用は、業者に頼むと工事費込みで5〜10万円程度が相場 です。設置場所や天井の材質、施工内容によっては価格が変動することがあります。断熱材を補強する作業や、天井の補修が必要な場合は追加費用が発生することもあります。
M Takihanaチャンネルさんの「点検口を作る!屋根裏作業の必需品点検口を作ってみました」の動画を紹介します。
DIYで屋根裏点検口の設置の仕方を詳しく解説されています。
点検口を後付けするオススメの場所と注意点
天井点検口の設置場所は、点検のしやすさと住宅のデザイン性の両方を考慮しましょう。適切な場所に設置することで、屋根裏の点検がスムーズに行え、住宅の機能性を維持しやすくなります。
1. 収納スペースの上(クローゼット・押し入れ)
最もオススメなのは、クローゼットや押し入れの天井 です。
この場所を選ぶことで、点検口が目立たず、インテリアを損なわないというメリットがあります。また、収納スペースなら荷物を移動させれば十分な作業スペースを確保しやすく、点検作業もスムーズに行えます。
2. 廊下の天井
廊下も、天井点検口の設置に適した場所の一つです。
廊下は家具が少なく、点検口の開閉や作業の邪魔になりにくいため、メンテナンスがしやすいというメリットがあります。ただし、天井の高さによっては脚立が必要になるため、安全性を考慮して設置場所を選ぶ必要があります。
3. 天井裏のスペースが広い場所
点検口は、屋根の傾斜が急な場所や梁が密集している場所では、点検口を開けても作業がしにくくなります。設置前に屋根裏の構造を確認し、点検作業がしやすい位置を選ぶことが大切です。
4.雨漏りなどの形跡のある場所の周辺
雨漏りの疑いのある場所のすぐ近くに設置することで、雨漏りの原因の追究などがやりやすくなります。雨漏りの原因の特定は1回ではできない場合もあるので、点検口をつけておくことで何度も確認できるようになり便利になります。
避けたほうがよい場所
- リビングや寝室の天井 → 目立ちやすく、デザイン性を損ねる可能性がある
- キッチンの真上 → 湿気や油汚れがたまりやすく、メンテナンス時に清掃が必要になる
- 天井裏に十分なスペースがない場所 → 点検作業が困難になり、十分な確認ができない
屋根裏の点検口がどこにあるかと一緒に知っておきたい知識

屋根裏の点検口は、収納スペースの上にあることがほとんどです。それと同時に点検する際の注意点などについても以下の点で解説します。
- 天井点検口のデメリットと注意点
- 屋根裏点検口の断熱材の影響とは
- 屋根裏を点検をする際の注意点
- 屋根裏を点検する時に用意するべきオススメの品
天井点検口のデメリットと注意点
天井点検口は屋根裏や配線の点検に役立つ設備ですが、デメリットや注意点があります。
- 断熱性能の低下の可能性
天井の点検口は、通常の天井と比べて気密性が低くなります。断熱材が適切に処理されていない場合、冷暖房の効率が下がり、光熱費が増加する可能性があります。気密性の高い点検口を選ぶ、断熱材を適切に配置するなどの対策が必要です。 - 防音性能の低下
天井に開口部を作ることで、屋根裏の音が部屋に響きやすくなることがあります。マンションや二世帯住宅など、上下階の騒音対策が重要な住宅では、防音対策が求められる でしょう。遮音材を使用した点検口や、気密パッキン付きの製品を選ぶことで、音漏れを軽減できます。 - 設置場所による見た目の影響
点検口は天井の一部に設置するため、設置場所によってはインテリアの見た目に影響を与えることがあります。リビングや寝室などの目立つ場所に設置すると、デザイン性が損なわれる可能性があるため、収納スペースや廊下など、目立ちにくい場所を選ぶとよいでしょう。 - 開閉時の安全性に注意
天井点検口を開ける際には、高い位置にあるため脚立や椅子を使用する必要があり、落下のリスクがあることも考慮しなければなりません。高齢者が点検を行う場合は、安全に作業できる環境を整えることが重要です。点検口の位置や開閉方法を工夫し、安全にアクセスできる設計にすると良いでしょう。
屋根裏点検口の断熱材の影響とは
屋根裏点検口の設置には、家の断熱性能への影響のがある場合もあります。
屋根裏の断熱材は住宅の温度管理に欠かせない役割を果たしており、不適切な点検口の設置や管理によって断熱性能が低下する可能性があります。点検口周辺の断熱材は開閉の際にズレたり圧縮されたりすることがあり、冷暖房の効率が下がって室内の温度が安定しにくくなることが考えられます。冬場の暖房時や夏場の冷房時には、光熱費の増加につながることもあるため注意が必要です。
屋根裏を点検をする際の注意点

屋根裏の点検は、住宅の状態を確認するうえで重要な作業ですが、実施する際にはいくつかの注意点があります。
誤った方法で点検を行うと、怪我や住宅の損傷につながることがあるため、安全に配慮しながら行うことが大切です。
まずは屋根裏には完全に入らない
屋根裏の床面は、歩行を想定して設計されていないため、誤って踏み抜くと天井が破損する恐れがあります。
そのため、まずは点検口から覗くだけにとどめるようにしましょう。
どうしても中に入る必要がある場合は、躯体部分の梁(はり)の上だけを慎重に歩くようにしましょう。下地や天井のボードの上は人が乗れるほどの耐久性がないので、下手すると天井が抜けて落下する可能性があります。
できる限り、一人が屋根裏に入るのであれば、もう一人は下で様子をみるなどして、複数人体制で行うようにしましょう。
電気配線には触れない
屋根裏には電気配線が通っており、劣化している配線に触れると感電のリスクがあります。特に、漏水の疑いがある場合は、感電の危険性が高まるため、専門業者に依頼する方が安全です。
カビやホコリの影響に注意
屋根裏は通気が悪いため、ホコリやカビが発生しやすい環境です。吸い込むとアレルギー症状を引き起こす可能性があるため、点検時にはマスクやゴーグルを着用し、必要に応じて換気を行うことが大切です。
懐中電灯を使って慎重に確認する
屋根裏は暗く、視認性が低いため、しっかりと照らしながら点検することが重要です。スマートフォンのライトでも確認できますが、より広範囲を照らせるLED懐中電灯を用意すると、見落としを防ぐことができます。
シロアリや害虫の痕跡や天井の雨漏り跡を見逃さない
屋根裏には、シロアリやネズミなどの害虫が侵入することがあります。
木材に穴が空いている、食害の跡がある、フンが落ちているなどの兆候が見られた場合は、害虫被害の可能性があるため、早めに専門業者に相談するのが賢明です。
天井に雨水の染みの跡や、水が漏れている場所がないか確認することも大切です。雨漏りが発生している場合、家の劣化も進み、シロアリの発生の原因などにもなるので、早めに専門業者などに相談して対処するようにしましょう。
安全対策を徹底する
点検口の開閉時や屋根裏に入る際は、転倒や落下に注意することが必要です。
脚立を使う場合は、安定した場所に設置し、無理な姿勢をとらないようにすることが重要です。また、一人で作業するのではなく、誰かにサポートしてもらうことで、安全性を高めることができます。
屋根裏を点検する時に用意するべきオススメの品
屋根裏を点検する際には、安全に作業を進めるための道具を事前に準備しておくことが重要です。屋根裏点検に役立つおすすめの道具を紹介します。
1. 懐中電灯またはヘッドライト
屋根裏は基本的に照明がないため、十分な光を確保することが必須です。
懐中電灯やスマートフォンのライトでも照らせますが、両手を使えるヘッドライトが特におすすめです。LEDタイプの明るいものを選ぶと、細かい部分までしっかり確認できます。
2. 防塵マスクとゴーグル
屋根裏にはホコリやカビが多く、吸い込むとアレルギー反応や呼吸器トラブルの原因になることがあります。
防塵マスク(N95規格推奨)を着用することで、ホコリや微粒子の吸引を防ぐことができます。また、ゴーグルを装着することで、目へのホコリの侵入を防ぐことができるため、安全性が向上します。
3. 手袋(作業用グローブ)
屋根裏には釘や木材のささくれがあるため、手を保護するための手袋が必要です。特に、断熱材の確認や配線の点検をする際には、手袋を装着しておくと怪我を防げます。滑り止め付きの作業用グローブを選ぶと、道具を扱いやすくなるため便利です。
4. 汚れてもいい長袖・長ズボンの作業着
屋根裏は狭いスペースが多く、木材や断熱材がむき出しになっていることがあります。ホコリなども多く貯まっており汚れるため、長袖・長ズボンの作業着を着用するのが望ましいでしょう。
5. 脚立(安定性のあるもの)
天井点検口から屋根裏にアクセスする際には、安定した脚立が便利です。不安定な台や椅子を使用すると、転倒のリスクが高まります。
高さを調整できるタイプの脚立を用意し、必ず平らな場所に設置して使用するようにしましょう。
6. スマートフォンやカメラ
屋根裏の状態を記録するために、スマートフォンやカメラで写真を撮ることをおすすめします。雨漏りや配線の損傷などを見つけた場合、写真を残しておくことで、後で専門業者に正確な状況を伝えることが可能になります。
【まとめ】屋根裏の点検口がどこにあるか探す方法

屋根裏の点検口は、メンテナンスを行うために必要なもので、収納スペースやクローゼットの天井、または廊下の一角に配置されていることが多くあります。
古い家の場合などには、設置されていない場合もあるので注意が必要です。屋根から雨漏りが発生した場合など、点検口がないと発生場所の特定もしにくくなるので、後付けでも設置することをオススメします。
- 屋根裏点検口は天井に設置される小さな開口部
- 収納スペースや廊下の天井に設けられることが多い
- クローゼットや押し入れの天井に設置されることが一般的
- 廊下や居室の天井にあるケースもある
- ロフトや屋根裏収納の中に設置されることもある
- 点検口がない住宅も存在し、義務ではない
- 「長期優良住宅」や「フラット35」の基準では設置が推奨される
- 点検口がないと雨漏りや害虫被害の早期発見が難しくなる
- 断熱材の劣化確認ができず、光熱費が増える可能性がある
- 点検口がない場合、天井の一部を解体する必要が出ることもある
- 天井点検口の後付けには5〜10万円程度の費用がかかる
- 断熱材のズレや気密性の低下に注意が必要
- 点検口の設置場所は収納スペースや廊下が推奨される
- 屋根裏に入る場合は、躯体部分(梁)の上を慎重に歩く