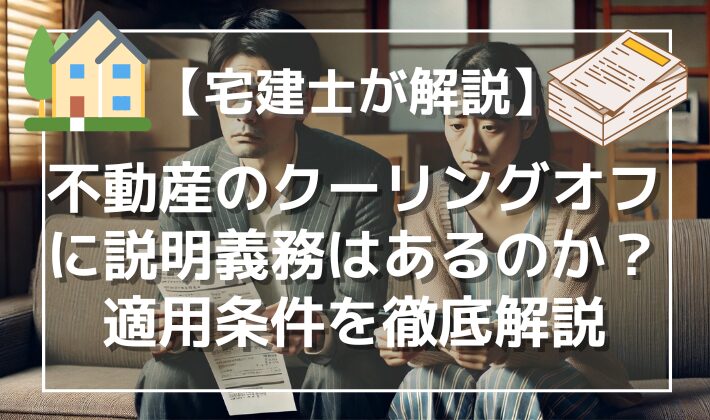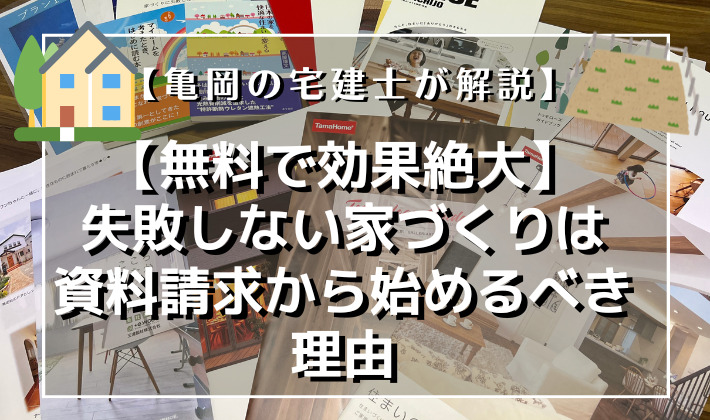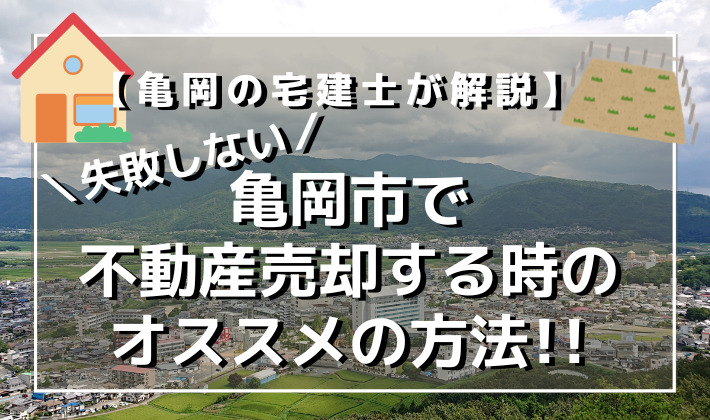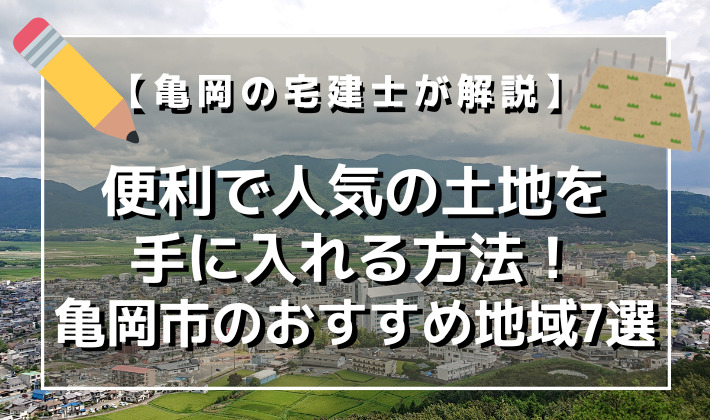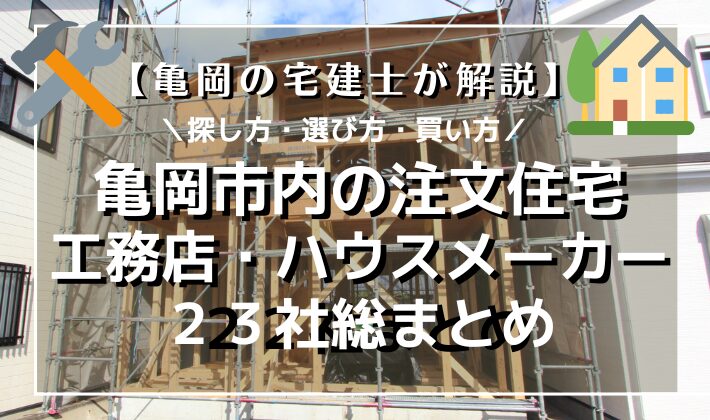不動産のクーリングオフで悩む人
「不動産のクーリングオフについて知らなかったんだけど説明義務はないの?」
クーリングオフは、特定の条件下で契約を解除できる重要な制度ですが、不動産取引において、クーリングオフについて説明を受けなった人は多いのではないでしょうか?
不動産のクーリングオフは、売主が宅地建物取引業者でなければ適用外となり、売主が個人で不動産業者が仲介に入っている場合では、別の方法でしかキャンセルできません。
また、売主が宅地建物取引業者であっても、申込や契約を業者の事務所で行った場合や、代金を全額支払い所有権移転をしている場合は対象外となるので、そもそもクーリングオフが適用されるケースが少なく、説明されないことが多くなっています。
クーリングオフが適用できる場合であっても、不動産会社がクーリングオフについて説明する義務はありません。
不動産を購入するためには、お金を用意する時間などが必要で、本当に必要な物なのかどうか考える時間も与えられます。最終的にお金を払う際には、司法書士に対して購入の意思表示をして署名捺印する必要もあるので、無理矢理購入させられた。とは考えにくいからです。
この記事では、クーリングオフできる条件やクーリングオフができない条件を明確に解説し、クーリングオフができない場合の解除方法についても詳しく紹介します。
また、クーリングオフをする場合の適切な提出方法や書面の記載事項のポイントについても触れ、スムーズに手続きを進めるための知識を提供します。不動産取引におけるトラブルを防ぎ、安心して契約を進めるための参考にしてください。

不動産のクーリングオフはできないケースが多々あります。対象外の場合は別の方法で解約する必要があります。
この記事のポイント
- 不動産のクーリングオフの説明義務の有無とその概要
- クーリングオフできる条件や適用される状況
- クーリングオフができない場合の具体的な理由や条件
- クーリングオフの適切な手続き方法と書面記載のポイント
>>不動産キャンセルのお詫びで重要なポイントと正しい対応方法>>
不動産のクーリングオフができる条件や説明義務の有無

- クーリングオフとは
- クーリングオフの効果
- 不動産業者はクーリングオフの告知を義務付けられていますか?
- 不動産のクーリングオフできる条件
- 不動産のクーリングオフができない条件
- クーリングオフが対象外の場合の解除方法
クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定の条件で契約を解除できる消費者保護の制度で、訪問販売や電話勧誘など、購入者が契約を急がされたり、不十分な説明を受けたりする場面を想定して設けられています。
不動産取引でも特定の場合に適用され、一定期間内であれば、解約することが可能です。
クーリングオフ制度は、契約者が冷静に判断できる環境を整えることを目的としています。高額商品や複雑な契約ほど、短期間での判断が求められると後悔する可能性が高まるため、このような保護措置が取られています。
クーリングオフの効果
クーリングオフを行うと、申し込みや契約した内容が無償で解約となります。
申込金や手付金などを支払っている場合は、すべて返還され、契約書の特約条項で、この内容を変更したとしても無効となります。

クーリングオフでをすることで、申込や契約が無かったことになり、支払ったお金もすべて戻ってきます。
不動産業者はクーリングオフの告知を義務付けられていますか?
不動産業者はクーリングオフについて告知義務はありません。
そもそもクーリングオフは、冷静に判断のできない場所で業者に言いくるめられ、その場のノリや勢いで申込や契約した場合にキャンセルできる仕組みです。
売主が個人で仲介業者が入っている場合や、業者の事務所で申込や契約を行う場合には、そもそもクーリングオフの対象とならない場合が多く、契約書にはその説明の記載の無い場合がほとんどです。
喫茶店やレストランなどで不動産申込や契約をした場合、クーリングオフの対象となりますが、その場合であっても告知する義務はありません。もしクーリングオフの説明を受けた場合8日以内であればクーリングオフ可能という条件が付きます。説明が無ければ代金を全額支払うまでならクーリングオフが可能です。
不動産は高額となることが多いので、申込や契約の時点からお金を用意するための期間ができ、その間に本当に必要な物なのかどうかを考える時間が与えられることになります。クーリングオフについての説明が無かったとしても、本当は不必要な物だったと考えるのであれば、クーリングオフを適用できるようになっています。
代金全額を支払って引渡しを受けてしまうとクーリングオフは出来なくなります。不動産を購入する際は司法書士に対して、購入の意思表示をして署名捺印をする必要があるので、すなわち納得して購入した。という判断がされてしまうからです。

クーリングオフはあくまで、立場の低い消費者が、冷静に判断せず申し込んでしまった物をキャンセルできる救済措置です。
不動産のクーリングオフできる条件

不動産のクーリングオフができる条件は、細かく規定されており、主に以下のようなケースです。
- 買主が個人である
- 売主は宅地建物取引業者である
- 申込や契約場所が事務所やモデルルーム以外
- 申込や契約場所がテント張りの案内所の場合
- 申込や契約場所が売主の提案で自宅や勤務先で行った場合
- クーリングオフの説明から8日以内
- まだ物件の引渡しは受けていない
- 代金全額を支払っていない
各項目を解説します。
買主が個人で売主が宅地建物取引業者であること
クーリングオフができる場合の大前提として「買主は一般の個人」で「売主は宅地建物取引業者」である必要があります。
宅地建物取引業者と個人とでは、不動産に対する知識のある宅建業者の方が有利となり、冷静に判断できないまま契約させられるようなことを防ぐためです。
申込や契約場所が業者の事務所やモデルルーム以外であること
不動産契約が業者の事務所以外、例えば喫茶店や訪問先などで締結された場合、消費者はクーリングオフの権利を行使できます。これは、営業所以外で契約が行われることで冷静な判断が難しくなる可能性を考慮しているためです。
テント張りの臨時の案内所や、継続的に業務行わない場所での契約もクーリングオフの対象となります。
申込や契約場所が売主から申し出て、買主の自宅や勤務先の場合
申込や契約をした場所が、買主の自宅や勤務先の場合で、その場所で契約しようと提案したのが売主側だった場合にクーリングオフの条件に当てはまります。
クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること
クーリングオフの通知は、クーリングオフの説明を受けから8日以内に書面で行う必要があります。この期間を過ぎるとクーリングオフは行えなくなります。
クーリングオフについての説明が無かった場合は、物件の引き渡しを受けるか、代金を全額支払うまでです。
引渡しを受けておらず、まだ全額を払っていない
まだ物件の所有権が買主に移っておらず、代金全額を支払っていない場合はクーリングオフの対象となります。
ただし、クーリングオフについての説明があった場合は、説明から8日経過していると対象外となります。
不動産のクーリングオフができない条件
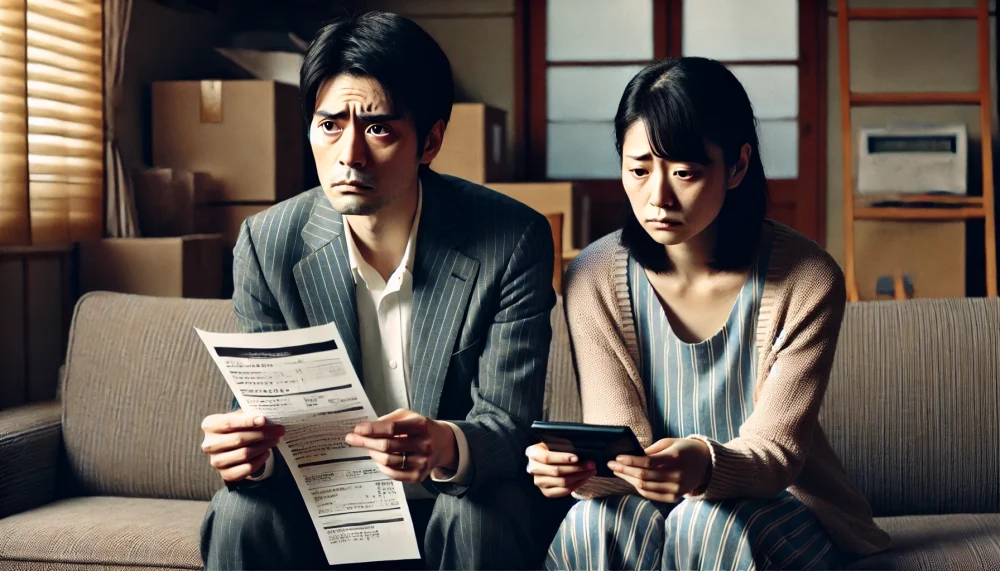
主に以下の状況に該当する場合、クーリングオフの権利は行使できません。
- 売主が個人の場合
- 買主が宅地建物取引業者の場合
- 契約場所が業者の事務所やモデルルームである
- 契約場所が買主の提案で自宅や勤務先の場合
- クーリングオフの説明から8日を経過している
- 引渡しが完了している
- 代金全額の支払いが完了している
- 商用目的の契約の場合
売主が業者ではなく個人である
不動産の売主が宅地建物取引業者ではなく、一般の個人だった場合クーリングオフは適用できません。
個人との間に不動産会社が仲介していたとしても対象外です。個人同士の取引であればパワーバランスが同じでだからです。
買主が宅地建物取引業者の場合
買主が宅地建物取引業者である場合も、クーリングオフは適用されません。
申込や契約場所が業者の事務所やモデルルームである場合
申込や契約が業者の事務所やモデルルームなど、営業活動を目的とした場所で行われた場合は、クーリングオフの対象外となります。これは、消費者が冷静に判断できる環境で契約を行ったと見なされるためです。
買主の提案で自宅や勤務先で申込や契約をした場合
買主の方から、自身の自宅や勤務先で契約や申込をすると提案してそれを行った場合は、クーリングオフの対象外となります。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合はクーリングオフは対象外です。
クーリングオフの説明から8日以上経過している
クーリングオフについて書面での説明がされた日から8日以上を経過した場合、クーリングオフの対象になりません。
説明がなかった場合は、物件の引渡しを受けるか、代金を全額支払うまでです。
引渡しを受け、代金全額の支払いを完了している
所有権の移転と代金全額の支払いが完了している場合、クーリングオフの対象になりません。
不動産を購入する際は司法書士に対して、購入の意思表示をして署名捺印をする必要があるので、すなわち納得して購入した。という判断がされてしまうからです。
商業用目的の契約の場合
買主が個人であっても、不動産が事業用の目的で購入される場合も、消費者保護の対象外とされるためクーリングオフはできません。個人の居住用ではなく、事業の一環とみなされる取引では、特別な保護が適用されないのが一般的です。

クーリングオフできることを知らないまま状況が進むと、強制的にクーリングオフできなくなる状況となってしまう。
クーリングオフが対象外の場合の解除方法
個人間の取引など、クーリングオフが適用されない場合でも、不動産契約には解除方法がいくつか存在します。
クーリングオフが使えない場合は、これらの方法を必要に応じて対応することが求められます。
- 申込から契約まで間は無償解除
買付確約書などを提出して申し込みをして契約するまでの間であれば、基本的にペナルティ無しで解約が可能です。
ただし、値引き交渉をしたり、契約の直前などは、相手方に迷惑を掛けてしまうことを覚悟して、解約しなければなりません。 - 手付解除による解約
契約時に手付金を支払っている場合に、一定の条件で手付金を放棄することで解約が可能です。
内容は契約ごとに変わるので契約書を確認するようにしましょう。 - 契約違反による解除
不動産業者が契約内容や法律に違反した場合、買主は契約を解除する権利を持つことがあります。例えば、重要事項説明書に虚偽の記載があった場合や、説明義務が果たされていなかった場合がこれに該当します。 - 手付解除期間後の解約
手付解除ができる期間を経過した場合、不動産契約には、あらかじめ解除に関する特約が定められています。特約に基づき、違約金の支払いを条件として契約を解除できます。契約内容により違約金の額も異なるので契約書を確認するようにしましょう。 - 融資利用の場合の特約による解除
買主が住宅ローンなどの融資を受けて不動産の購入をする場合に、一定期間を設けてその間に融資が受けられない場合に無償で解約することが可能です。
クーリングオフが適用されない場合でも、上記のような手段があるため、困った際には仲介業者などに相談して最適な方法を選びましょう。

契約解除にはルールや条件が決められており、場合によっては違約金を支払う必要もあり、慎重な対応が求められます。
不動産のクーリングオフのやり方や説明義務に関連する知識
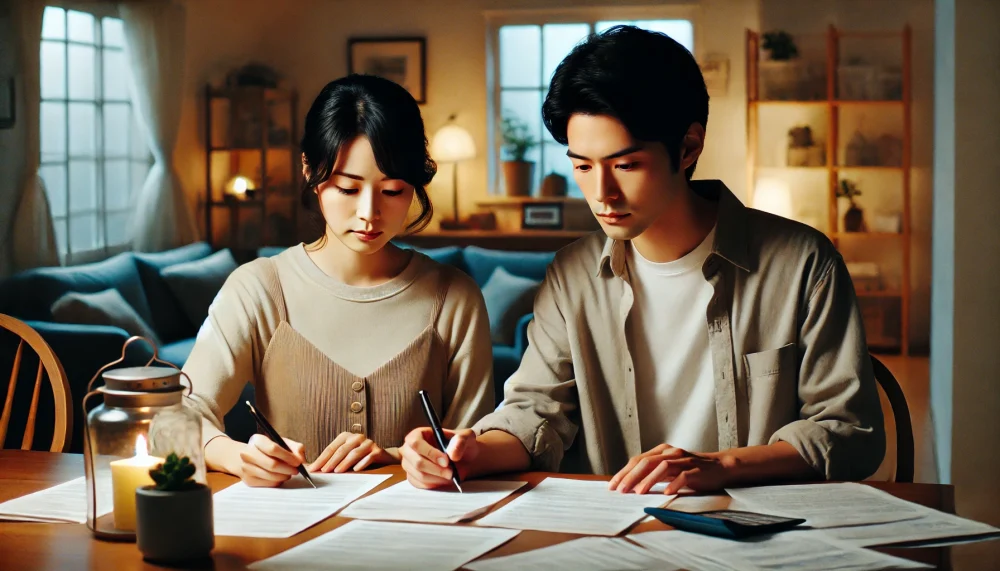
実際にクーリングオフする場合の知識や、それに関連した知識を以下の点で解説します。
- クーリングオフにおける適切な提出方法
- クーリングオフの書式とは?
- クーリングオフ書面の記載事項のポイント
- クーリングオフしない為にできること
- クーリングオフの説明が無いのは違法ではない
- 不動産の仲介の場合はクーリングオフできない場合が多い
クーリングオフにおける適切な提出方法
クーリングオフを実施する際は、提出方法にも注意が必要です。不動産取引の場合、適切な手順を踏まなければクーリングオフが無効となる可能性があるため、以下のポイントを確認しましょう。
- 書面で通知することが基本
クーリングオフは口頭での申し出では認められません。必ず書面にて、契約の解除を通知する必要があります。この書面には必要な情報を明記し、不備がないように作成することが重要です。 - 書面の送付先を確認する
書面は、不動産業者の営業所や本社に送付するのが一般的です。ただし、契約書に特定の送付先が記載されている場合は、その指示に従う必要があります。送付先の確認を怠ると、解除の意思表示が適切に届かない可能性があります。 - 郵送方法を慎重に選ぶ
書面の送付には、証拠を残すために内容証明郵便や配達証明郵便を利用することが推奨されます。これにより、送付した日時や内容を証明できるため、トラブルを未然に防ぐことができます。 - 期限を守ることが不可欠
クーリングオフの説明を受けてから8日以内に行う必要があります。この期限を過ぎると解除権が失効するため、日にちを正確に把握しておくことが重要です。郵送した場合は、書面を郵便に出した日が適用されます。 - 弁護士や専門家に相談する
提出方法や内容に不安がある場合は、弁護士や消費者センターに相談することで、正確なアドバイスを得ることができます。これにより、クーリングオフが確実に成立する可能性が高まります。
クーリングオフは法的手段ですが、提出方法のミスが原因で無効になるケースもあります。手続きの正確さを心がけましょう。
クーリングオフの書式とは?
クーリングオフに必要な書式には、契約解除を明確に伝えるための基本的な項目が含まれていれば問題ありません。
- 書式に含めるべき情報
クーリングオフの書面には、以下の内容を記載する必要があります。- 契約の解除を求める旨(例:「契約解除のご通知」など)
- 契約日と契約内容の詳細(物件名や契約番号など)
- 契約者(買主)の氏名と住所
- 書面作成日と署名または押印 これらを簡潔かつ明確に記載することで、クーリングオフが無効とされるリスクを減らせます。
- 契約した不動産の情報(所在地・地目・地積・建物の種類・建物面積など)
- 形式に特別なルールはない
書式には特定のフォーマットが法律で定められているわけではありません。
手書きでも問題ありませんが、読みやすく整った形式で作成することが望ましいです。 - 注意点として書面の不備を防ぐ
記載内容に誤りがあると、意思表示が正確に伝わらずトラブルの原因となります。例えば、契約日を間違えた場合や、署名を忘れた場合などが挙げられます。 - 内容証明郵便を利用する
書式が正確に整っていても、書面が業者に届かなければ意味がありません。提出方法と併せて、郵便による証明を活用することで確実に意思を伝えられます。説明を受けてから8日以内が期限となり、郵便の場合は、発送した日が適用されます。

実際にクーリングオフをする場合は、業者側に書類を作ってもらい、そのまま提出するのが一般的です。
クーリングオフ書面の記載事項のポイント
クーリングオフの書面を作成する際は、記載内容が正確であることが重要です。不備があると、契約解除が無効とされる場合があるため、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 契約解除の意思を明確に示す
書面の冒頭には、「契約を解除する」という意思を明確に記載します。具体的には「本契約をクーリングオフに基づき解除します」といった表現が適切です。この記載により、相手方に誤解を与えることなく、意思を伝えることができます。 - 契約の詳細情報を記載する
契約解除対象の特定が必要です。物件名、契約日などの詳細情報を正確に記載してください。この情報が不足していると、どの契約を解除するのか分からず、無効になる可能性があります。 - 提出者の情報を記載する
契約解除を申し出る者の氏名、住所、連絡先を記載することで、相手方が速やかに対応できるようになります。また、署名または押印を忘れずに行い、正式な書面として整えることが求められます。 - 提出日を明記する
クーリングオフは期限内に通知する必要があります。そのため、提出日を正確に記載することで、解除通知が有効であることを証明することができます。提出日が抜けている場合、通知が期限外と判断されるリスクがあります。 - 丁寧で読みやすい形式にする
内容が分かりにくいと、業者側が対応を誤る可能性があります。箇条書きや段落ごとに分けるなど、読みやすさを工夫することも重要です。
書面作成は契約解除を確実にする第一歩です。正確な情報を盛り込み、法律に基づいた形式を整えることで、スムーズな手続きを目指しましょう。
クーリングオフしない為にできること

クーリングオフを避けるためには、契約時の慎重な判断と事前の準備が重要です。
不動産取引は高額で複雑な契約が伴うため、以下の対策を講じることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
事前に十分な情報を収集する
申込や契約を結ぶ前に、物件の詳細情報や契約内容をよく確認しましょう。物件の立地や価格、法律的な制約などを把握することで、後から「聞いていなかった」という問題を回避できます。
契約前に疑問点や懸念点を担当者に質問し、すべて解消しておくことが大切です。特に手数料や解除条件については詳しく確認しておきましょう。不安な点をそのままにして契約を結ぶと、後で後悔する可能性が高まります。
不動産購入に必要な費用総額を確認しておく
キャンセルしたい理由で多いのが「当初の予定より多くの資金が必要だった」「予算オーバーになってしまった」ということが挙げられます。
申込や契約を結ぶ前に、必ず不動産を購入するのに必要となる金額のすべてを見積もりしてもらうようにしましょう。

注文住宅などは、オプションの追加などで当初の予定より金額が上がることが多くなっています。
事前にオプションも含めて予算感を確認しておくようにしましょう。
周囲のアドバイスを受ける
契約を急がされる場合でも、専門家や信頼できる人に相談する時間を確保しましょう。弁護士や宅建士のような専門家から助言を受けることで、冷静な判断がしやすくなります。
不動産業者が信頼できるかどうかも重要なポイントです。口コミや評判を調べ、過去にトラブルがなかったか確認しておくことで、不安を軽減できます。

とにかく、勢いやノリで申込や契約をしないことが重要です!不動産は高額なのでよく考えてから進めるようにしましょう。
クーリングオフの説明が無いのは違法ではない
クーリングオフについての説明が無くても違法ではありません。
- 宅建業法で定められた義務
不動産業者は、特定の条件下でクーリングオフについて説明する義務を負っています。例えば、事務所以外の場所で契約が行われた場合や、訪問販売のような状況で契約が締結された場合などが該当します。これに該当しない場合は、説明が省略されるケースもあります。 - 説明が無かった場合の対処法
クーリングオフについて説明を受けていないと感じた場合、まずは契約書や交付書面を確認しましょう。
書面に記載が無い場合でも、クーリングオフが可能な条件下であれば、書面で解除を申し出ることで対応できます。また、弁護士や消費生活センターに相談することで、適切な手続きを進められます。 - 消費者としての心得
クーリングオフについての説明が無かった場合でも、すぐに「違法」と判断するのではなく、まず状況を正確に把握することが大切です。業者の対応を冷静に確認し、必要に応じて法的手段を検討しましょう。
説明の有無に関係なく、クーリングオフが行使できる条件を理解しておくことで、契約トラブルを未然に防ぐことができます。
不動産の仲介の場合はクーリングオフできない場合が多い
不動産のクーリングオフは、売主が宅地建物取引業者であることが大前提なので、個人が売主であることが多い仲介の場合は対象外となってしまします。
売主が個人の場合でも、物件現地で不動産業者に乗せられて冷静な判断ができない状態で申込をした。というシチュエーションもあるかもしれませんが、そんな場合でもクーリングオフはできません。
仲介の場合、申込後で契約をする前であれば、法的効力はないのでキャンセルは可能です。ただし、値引き交渉の後や、契約の直前というタイミングでのキャンセルは、個人の売主にも迷惑を掛けることになる。ということを承知して行わなければなりません。

どちらにしろ、購入の判断はよく考えてから行うことが重要です。必要ない物に申込をしてしまったのであれば、売主に迷惑を掛けたとしてもキャンセルしないと自分が後悔することになります。
【まとめ】不動産のクーリングオフには説明義務はあるのか

不動産のクーリングオフは、売主が宅地建物取引業者でなければ適用外となり、売主が個人で不動産業者が仲介に入っている場合では、別の方法でしかキャンセルできません。
売主が宅地建物取引業者であっても、申込や契約を業者の事務所で行った場合や、代金を全額支払い所有権移転をしている場合は対象外となるので、そもそもクーリングオフが適用されるケースが少なく、説明されないことが多くなっています。
基本的に不動産業者がクーリングオフについて説明する義務はありません。
不動産の契約解除が必要なのであれば、別の方法で解約をするように手続きしましょう。

クーリングオフは、立場の低い消費者が、冷静に判断せず申し込んでしまった物をキャンセルできる救済措置です。
- クーリングオフは消費者保護のための契約解除制度
- 不動産業者はクーリングオフの説明の義務はない
- 売主が宅地建物取引業者でなければクーリングオフはできない
- 売主が個人で仲介業者が入っている場合は、クーリングオフ対象外
- 事務所やモデルルーム以外の場所で申込や契約をした場合クーリングオフ可能
- 買主の提案で事務所以外の場所で申込や契約をした場合クーリングオフは対象外
- クーリングオフの説明後8日以内であればがクーリングオフが可能
- クーリングオフの説明が無ければ、代金を全額支払うまでなら可能
- クーリングオフの対象外の場合は、別の方法で契約を解除する
- 書面での通知がクーリングオフには必要
- 書面の送付は内容証明郵便を利用するのが望ましい
- 郵便に出した日が通知した日になる
- 引渡しや代金全額支払い後はクーリングオフ不可
- 買主が宅地建物取引業者の場合はクーリングオフ不可
- 商用目的の契約にはクーリングオフは適用されない